- 連作障害とは?
- 起きやすい科と回避の年数目安
- 症状の見分け(肥料不足や乾燥と混同しがち)
- 畑とプランターの違い(ベランダは実は“連作が出やすい”)
- よくある誤解(ミスを先回りで回避)
- 輪作設計の基本
- テンプレ①|3畝(最小構成)で回す
- テンプレ②|4畝(王道ローテ)
- テンプレ③|超小区画(1〜2畝)でも回したい
- テンプレ④|プランター/ベランダの輪作と土の回し方
- 科の早見とカテゴリ連動(サイト内の導線に)
- 季節ローテの実例(温暖地目安)
- 接ぎ木苗の活用(特にナス科・ウリ科)
- 抵抗性品種・病害回避型の選択
- 太陽熱消毒(家庭向けNo.1の土壌消毒)
- バイオフュミゲーション(緑肥マスタード等)
- pH・CEC・団粒の立て直し
- 排水と灌水の最適化(病害のトリガーを絶つ)
- 微生物資材の併用
- 衛生(サニテーション)でリスクを減らす
- 代表病害の“土づくり的”対策まとめ
- 【保存版】連作障害っぽい時の診断フロー
- 運用テンプレ|いますぐ・今週・今季やること
- よくあるQ&A
- チェックリスト(印刷推奨)
- まとめ|“設計×衛生×土台”で連作障害をコントロール
連作障害とは?
同じ科の野菜を同じ場所で続けて育てると、土のバランスが崩れて生育不良や病害が増える現象。原因は1つではなく、以下の複合要因です。
- 土壌病害の蓄積:特定作物を好む病原菌・線虫が増殖(例:ナス科の萎凋・青枯、アブラナ科の根こぶ病)。
- 土中微生物相の偏り:作物の根分泌(根から出る糖や有機酸)が偏り、相性の悪い菌が勢力拡大。
- 養分の偏りと塩類集積:特定要素の欠乏/過剰、液肥・化成の与え方でEC(肥料濃度)が上昇。
- 土の物理性悪化:踏圧や過湿で団粒が壊れ、根が酸素不足に。
- アレロパシー(他感作用):一部植物は他植物の発芽・生長を抑える物質を土壌中に残すことがある。
起きやすい科と回避の年数目安
原則は同じ科を2〜4年あける(作物や地域・土質で前後)。目安表:
| 科 | 代表作物 | 連作回避の目安 | 注意病害・メモ |
|---|---|---|---|
| ナス科 | トマト・ナス・ピーマン・ジャガイモ | 3〜4年 | 萎凋・青枯・そうか(ジャガ)/接ぎ木・太陽熱有効 |
| アブラナ科 | キャベツ・ブロッコリー・ダイコン・コマツナ | 3年以上 | 根こぶ病(pHやや高めで抑制) |
| ウリ科 | キュウリ・カボチャ・スイカ・メロン | 2〜3年 | つる割・根腐れ/排水・接ぎ木 |
| セリ科 | ニンジン・パセリ・セロリ | 2〜3年 | 連作で奇形・生育停滞が出やすい |
| ヒユ科 | ホウレンソウ・フダンソウ | 2〜3年 | 酸性土に弱い/pH管理が最重要 |
| マメ科 | エダマメ・インゲン・ソラマメ | 1〜2年 | 比較的強いが立枯や根粒菌の偏りに注意 |
| ユリ科ほか | ニンニク・タマネギ・ネギ | 2〜3年 | 白色疫病・乾腐/水はけ・風通し |
※ 香味野菜(パクチー等)はセリ科、ハーブ類は科がバラバラ。科が同じなら連作カウントに含めます。
症状の見分け(肥料不足や乾燥と混同しがち)
- 連作障害っぽい:活着後に急激な萎れ、下葉から枯れ上がる、同じ畝の同じ位置で毎年不調。
- 肥料不足:葉色が全体に淡い。追肥で回復傾向。
- 乾燥・過湿:日内変動(朝元気・昼しおれ・夕方回復)/大雨後に根ぐされ。
畑とプランターの違い(ベランダは実は“連作が出やすい”)
- 土量が少ない→微生物相が偏りやすく、病原体の密度が上がる。
- 塩類の洗い流しが起こりにくい→EC上昇で根傷み。
- こまめな土の再生・太陽熱消毒・土替えが効果的。

とまとま
「同じ科を続けない」が合言葉!まずは科分けと回す年数を覚えよう〜
よくある誤解(ミスを先回りで回避)
- 誤)科さえ変えれば何でもOK → 正:科が違っても土壌病害の種類はまた別。排水・pH・団粒など土台が崩れていれば発生。
- 誤)石灰を大量に入れ続ければ防げる → 正:pH過剰で微量要素欠乏に。測って微調整が基本。
- 誤)未熟堆肥をたくさん入れれば土は強くなる → 正:ガス障害・病害の餌。完熟堆肥のみ。
輪作設計の基本
輪作は「土の都合を優先」して並べるのがコツ。作物の組み合わせは科と生育タイプ(果菜・葉菜・根菜・豆)を軸にします。
- 果菜(ナス科・ウリ科)→ 葉菜(アブラナ科・ヒユ科)→ 根菜(セリ科・アブラナ科)→ 豆(マメ科)→(必要なら緑肥)
- 多雨地:高畝+明渠設計をセットで。乾燥地:低畝+有機物マルチ。
テンプレ①|3畝(最小構成)で回す
| 年 | 畝A | 畝B | 畝C | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 果菜(トマト/ナス/キュウリ) | 葉菜(キャベツ/ホウレンソウ) | 根菜(ダイコン/ニンジン) | 畝肩に明渠・病残渣は持ち出し |
| 2年目 | 豆(エダマメ/インゲン) | 果菜 | 葉菜 | 豆で窒素補い、跡地は堆肥少なめ |
| 3年目 | 根菜 | 豆 | 果菜 | 根菜は元肥控えめ・土塊を除く |
テンプレ②|4畝(王道ローテ)
| 年 | 畝A | 畝B | 畝C | 畝D | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 果菜(ナス科/ウリ科) | 葉菜(アブラナ科) | 根菜(セリ/アブラナ) | 豆(マメ科) | 豆の後地はリン酸控えめ |
| 2 | 葉菜 | 根菜 | 豆 | 果菜 | 病残渣は場外へ |
| 3 | 根菜 | 豆 | 果菜 | 葉菜 | 緑肥を挟んで地力回復も◎ |
| 4 | 豆 | 果菜 | 葉菜 | 根菜 | 4年で1周:連作負荷を分散 |
テンプレ③|超小区画(1〜2畝)でも回したい
- 1畝型:春夏=果菜 → 秋冬=葉菜 or 根菜 → 翌年=豆+緑肥 → 次年=果菜
- 2畝型:畝A:果菜→豆→根菜→葉菜、畝B:葉菜→根菜→豆→果菜(互い違い)
- 栽培中も混植で負荷分散:例)トマト畝にバジル、キャベツ畝にレタス等。
テンプレ④|プランター/ベランダの輪作と土の回し方
- 容器を3グループに分ける(A:果菜用、B:葉菜用、C:根菜用)。
- シーズンごとに容器ラベルを回す:A→B→C→A…。土も容器内で回す。
- シーズン終わりに太陽熱消毒 or 熱湯処理→再生材(赤玉/くん炭/堆肥)で配合更新。
- 3サイクル目で50%以上新土を目安に。ECが高いと感じたら洗い流し灌水。
科の早見とカテゴリ連動(サイト内の導線に)
| サイトカテゴリ | 主な科 | 代表作物 | 内部リンク例 |
|---|---|---|---|
| kasairui(果菜類) | ナス科・ウリ科ほか | トマト・ナス・ピーマン・キュウリ | 果菜類まとめ |
| konsairui(根菜類) | セリ科・アブラナ科ほか | ダイコン・ニンジン | 根菜類まとめ |
| yousairui(葉菜類) | アブラナ科・ヒユ科ほか | キャベツ・ホウレンソウ | 葉菜類まとめ |
| herbs-koumiyasai(香味) | セリ科・シソ科 など | パクチー・バジル | 香味野菜まとめ |
| grow-calendar | 季節別 | 時期全般 | 育て方カレンダー |

とまとま
「畝に年札」を立てておくと、去年何を作ったか一目で分かるよ!
季節ローテの実例(温暖地目安)
- 春夏:トマト・キュウリ → 秋冬:ハクサイ・ブロッコリー → 翌春:ニンジン・ダイコン → 初夏:エダマメ → 次夏:トマト…
- 多雨地:高畝+黒マルチ+畝間明渠で病害圧を下げる。
接ぎ木苗の活用(特にナス科・ウリ科)
- 連作に強い台木に穂木をのせた苗。根の病害(つる割・萎凋・青枯)に耐える。
- 初期コストは上がるが失敗率が大幅減。狭い畑やプランターでは特に有効。
抵抗性品種・病害回避型の選択
- 種袋の表示(例:F(萎凋)・V(半身萎凋)・N(センチュウ)耐性など)を確認。
- アブラナ科は根こぶ抵抗性品種、ネギ類は白絹・さびに強い品種などを選ぶ。
太陽熱消毒(家庭向けNo.1の土壌消毒)
- 畝に十分灌水し、透明ビニールを密着させて覆う(隙間を減らす)。
- 真夏に2〜4週間。途中で表土を混ぜ直して熱ムラを減らす。
- 終わったらビニール撤去→軽く耕して次作へ。
利点:病原菌や線虫密度を下げ、雑草種子も減る。
注意:温度が上がり切らない時期は効果が鈍いので、薄く・長めを意識。
バイオフュミゲーション(緑肥マスタード等)
- カラシナ・シロガラシなどのグルコシノレート系緑肥を育て、開花前に細断→すき込み。
- 分解時に生じる成分で一部土壌病害を抑制する効果が期待できる(強制消毒ではない)。
- すき込み後は2〜3週間の分解期間を置いて窒素飢餓を回避。
pH・CEC・団粒の立て直し
- pH:多くの野菜は6.0〜6.5。アブラナ科は6.5付近、ジャガイモはやや酸性可。測って微調整。
- CEC(養分保持力):完熟堆肥・腐葉土・ゼオライトで底上げ。砂質は特に効果。
- 団粒化:完熟堆肥2〜3kg/m²+くん炭・バークで通気と保水の両立を狙う。
排水と灌水の最適化(病害のトリガーを絶つ)
- 高畝+畝間明渠:大雨時の滞水をゼロに。
- 黒マルチで土はね防止→葉の病害を減らす。
- 乾燥地は有機マルチで表土の硬化と水切れを防ぐ。
微生物資材の併用
- Bacillus/Trichoderma系など、土壌で拮抗する微生物資材を活着期に土壌灌注。
- 即効の“薬”ではないので、土台(排水・pH・団粒)を整えた上で補助的に使う。
衛生(サニテーション)でリスクを減らす
- 病気の出た残渣は畑外に持ち出す(堆肥化せず廃棄)。
- 支柱やハサミは消毒(アルコール等)。
- 水やりは株元から静かに(泥はね=病原の拡散)。
代表病害の“土づくり的”対策まとめ
| 病害 | 起きやすい作物 | 土づくり対策 | 奥の手 |
|---|---|---|---|
| 根こぶ病 | アブラナ科 | pHやや高め維持、排水、緑肥・輪作 | 抵抗性品種・太陽熱 |
| 萎凋・青枯 | ナス科 | 高畝・排水・土はね防止 | 接ぎ木苗・太陽熱 |
| つる割 | ウリ科 | 団粒化・排水・温度ムラ回避 | 接ぎ木・太陽熱 |
| 白絹・菌核 | 広範 | 通風・株間・マルチ | 残渣徹底持ち出し |

とまとま
「輪作+排水+太陽熱+接ぎ木」。狭い畑でも、この四天王でだいたい何とかなる!
【保存版】連作障害っぽい時の診断フロー
- 場所特定:毎年同じ畝・同じ位置で発生? → Yesなら土壌要因濃厚。
- 水と物理性:大雨後に滞水? スコップが30cm入る? → Noなら排水・耕盤対策。
- pH:6.0〜6.5付近? → 外れていれば石灰・堆肥で調整。
- 病徴確認:根がこぶ状、導管褐変、地際の白菌糸など(病名の当たりをつける)。
- 対策選択:輪作延長/接ぎ木/太陽熱/緑肥→すき込み/抵抗性品種。
- 翌年へ記録:畝札+ノートに「栽培作物・症状・処置・結果」を記録。
運用テンプレ|いますぐ・今週・今季やること
いますぐ(当日中)
- 病気の残渣を場外へ持ち出し。
- 畝間に逃げ水路を仮設(大雨の翌日に有効)。
- 泥はね抑制の黒マルチ/敷きわらを追加。
今週(1〜2週間)
- pH測定→必要なら苦土石灰(100〜150g/m²目安)。
- 団粒回復:完熟堆肥2〜3kg/m²+くん炭少量を鋤き込み。
- プランターは太陽熱消毒 or 熱湯処理で土をリセット。
今季(シーズン中)
- 同科を避けて短期作へ変更(例:葉物へシフト)。
- 接ぎ木苗・抵抗性品種を優先採用。
- 収穫後は緑肥(マスタード/ライ麦)で土を休ませる。
よくあるQ&A
Q1. 場所が狭くて輪作が回せません。
接ぎ木・緑肥・太陽熱の三本柱に加え、プランター併用で畝の負荷分散を。畝内混植(バジル/ネギ/レタス)も効果。
Q2. 何年あけても再発します。
排水・通気・pHの基礎に戻る。硬盤破砕(フォーク揺すり)/高畝化/団粒回復をセットで。
Q3. 石灰は毎年のルーチンでOK?
NG。測って微調整が基本。過剰石灰は微量要素欠乏を招く。
Q4. 有機肥料なら入れ過ぎても大丈夫?
未熟や過剰はNG。塩類集積と病害の温床に。完熟を適量、分割施肥が安全。
Q5. ベランダのコバエ・立枯れが止まりません。
表土を乾かしやすい配合にし、マルチで産卵を抑制。太陽熱、再生材(赤玉/くん炭/堆肥)で配合更新、月1の洗い流し灌水でECを下げる。
チェックリスト(印刷推奨)
- 科別に畝札&ノート管理(作付・病徴・処置・結果の4点)
- シーズン前pH・透水テスト/多雨期の高畝・明渠
- 残渣の場外処分/道具の消毒
- 緑肥の挿入(秋まきライ麦・春まきマスタード)
- 接ぎ木・抵抗性品種の優先採用
- プランター:土再生→3サイクルで50%以上新土
まとめ|“設計×衛生×土台”で連作障害をコントロール
- 同じ科を避ける輪作を軸に、排水・団粒・pHの土台をキープ。
- 狭い畑は接ぎ木・太陽熱・緑肥の合わせ技でリスクを下げる。
- 記録と見直しを続けるほど、再現性のある“強い畑”になる。

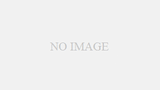
コメント