家庭菜園の肥料まとめ|種類・使い分け・施肥量とタイミング完全ガイド
「何を・どれくらい・いつ与える?」に迷わないための決定版。本ガイドは、N(窒素)・P(リン酸)・K(カリ)の役割と、pH・EC・有機/化成・元肥/追肥の設計を、庭・畑・プランターすべてで再現できる形に整理しました。欠乏や過剰の診断→応急処置→再発防止まで一直線に解説します。
- N-P-Kの効かせ分け(葉・根・実)と、マグネシウム/カルシウム/微量要素の位置づけ
- 有機肥料と化成肥料の違い、緩効性・被覆・液肥の使い分け
- 元肥/追肥の設計テンプレ(畝・株・プランター別)と失敗しない量の決め方
- pH/EC管理・石灰資材・塩類集積・肥料焼け対策
N・P・Kと二次要素・微量要素の役割
| 元素 | 主な働き | 増やすと | 不足すると |
|---|---|---|---|
| N(窒素) | 葉・茎の生育、タンパク合成 | 葉が茂る/色濃い | 黄化・生育停滞 |
| P(リン酸) | 花芽形成、根張り、エネルギー | 実付き/根張りUP | 着花不良・発色悪化 |
| K(カリ) | 耐病性、糖移行、気孔制御 | 甘味/充実/耐暑寒 | 葉縁枯れ・徒長 |
| Ca(石灰) | 細胞壁/根の活着 | 尻腐れ予防 | 尻腐れ・芯腐れ |
| Mg(苦土) | 葉緑素の中心 | 光合成UP | 葉間黄化(古葉から) |
| S・Fe・Mn・B・Zn・Mo | 酵素/成長調節 | 欠乏矯正 | 新芽黄化・奇形・花落ち等 |
pH(酸度)・EC(肥料濃度)の目安
- 畑/庭土のpH(H2O)目標:6.0〜6.5(イモ・根菜は6.0前後、葉菜は6.0〜6.5、果菜は6.5近辺)
- プランターのEC目標:生育期 0.8〜1.2 mS/cm(作物で調整)。高すぎ=塩類集積リスク。
- 石灰は播種/定植2週間以上前に。苦土石灰=pH矯正+Mg補給、消石灰は即効だが扱い注意。

pHは“土の器のサイズ”。器が小さいと肥料が効かないよ。まずpH→次に肥料、が鉄則!
有機肥料と化成肥料の違い(誤解を解く)
| 区分 | 代表例 | 効き方 | 利点 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 有機肥料 | 油かす・魚粉・骨粉・鶏糞・米ぬか・堆肥 | 微生物分解→無機化して効く(温度依存) | 土団粒化・微生物相が育つ | 低温期は効き遅れ・過湿で臭気 |
| 化成肥料 | 高度化成(例: 14-14-14)・単肥(硫安/過リン酸/硫酸カリ等) | 即効〜準速効(溶解→吸収) | 量の制御が簡単・安定 | 入れ過ぎ=塩類集積・肥料焼け |
| 緩効性/被覆 | マイクロ粒/コーティング粒(IB/LPコート等) | 温度×時間で徐放 | 施肥回数削減・効きムラ減 | 気温低いと効き遅れ |
| 液体肥料 | ハイポ系・魚由来液肥 | 即効(葉面/根圏) | プランターの微調整に最適 | 濃度過多に注意(EC) |
代表的な単肥・資材の性格
- 窒素源:硝酸態(速効・夏向き)/アンモニア態(やや緩効)/尿素態(土中で変換)
- リン酸:過リン酸石灰(速効)・溶リン(酸性土で効きやすい)
- カリ:硫酸カリ(無塩素)・塩化カリ(安価だが塩素で感受性作物注意)
- 石灰資材:苦土石灰(Mg供給)・消石灰(速効)・炭酸カルシウム(穏やか)
- 堆肥:土の物理性・生物性を上げる“地力の母”。肥料ではなく土づくり資材(NPKは低い)。
「土の温度」と「肥料の効き」
有機肥料の効きは微生物の仕事に依存。地温が上がるほど効き出しが早い。春先の立ち上がりは、緩効性+少量の即効分でブーストすると安定。
ラベルの読み方(保証成分)
例:14-14-14 はN・P2O5・K2Oのパーセント。必要量(g)=Nを基準に逆算すると過剰を防げます。
3つの設計層:土・作物・器(畝/鉢)
- 土:pHと有機物量(堆肥)で“器”を整える。
- 作物:葉菜=N多め/果菜=P・KとCa/根菜=KとP。
- 器:畝幅・株間・鉢サイズで面積/容量換算を行う。
元肥・追肥の考え方
- 元肥:定植時に効きすぎないよう緩効性中心。根に触れないよう“植穴から離して”施す。
- 追肥:生育ステージごとに少量多回。乾いた土に施し、必ず潅水。
作物別・標準テンプレ(庭・畑)
| 区分 | 元肥(m²あたり) | 追肥の目安 | メモ |
|---|---|---|---|
| 葉菜(レタス/ホウレンソウ) | 堆肥1〜2kg+緩効性NPK(合計Nで5〜8g) | 収穫始期にN中心で小分け | 過剰Nは病害招く |
| 果菜(トマト/ナス/ピーマン) | 堆肥2kg+緩効性NPK(Nで8〜12g)+苦土石灰 | 開花・着果ごとにNPK均衡+Ca補強 | 尻腐れ→Ca/潅水リズム |
| 根菜(ダイコン/ニンジン) | 堆肥1kg+P・K中心(Nは控えめNで3〜5g) | 基本少なめ。葉色見ながら1回 | 窒素過多=裂根・葉ばかり |
| イモ類(ジャガ/サツマ) | 堆肥1〜2kg+K多め(N抑え) | ジャガ:蕾期に一度/サツマ:基肥中心 | N過多はツルぼけ |
プランターのEC管理と液肥レシピ
- スタート:市販培養土+元肥入り(緩効性)を選ぶと初期は追肥ゼロでOK。
- 生育期:1〜2週間おきに既定の半分濃度から。受皿に溜めない(塩集中を防ぐ)。
- リセット潅水:月1回、鉢容量の2〜3倍の水を流して塩類洗い流し(白い析出=塩類集積)。
「量の決め方」逆算テンプレ(例)
例:トマト2株・幅60cm×長さ2mの畝(1.2m²)。
標準N目安=10 g/m² → 1.2m²でN=12g。
使う肥料が 14-14-14 の場合、その14%がNなので、必要肥料量 ≒ 12 ÷ 0.14 ≒ 85.7g(端数は85〜90g)。
→ これを元肥6割・追肥4割に分け、追肥は開花・着果ごとに小分けします。
追肥カレンダー(例:中間地・トマト)
- 定植2週間後:活着確認。葉色と生長を見て微量(液肥)
- 1段花房開花期:固形少量+潅水で溶かす
- 着果肥大期:同量またはやや増
- 以降、収穫継続中は2〜3週間ごとに葉色観察で微調整
欠乏・過剰の早見表(典型症状)
| 要素 | 欠乏症状 | 過剰症状 | 対処 |
|---|---|---|---|
| N | 全体黄化・生育停滞 | 徒長・病害増・実付き低下 | 速効Nを少量追肥/過剰は水やりで洗浄 |
| P | 葉が暗緑〜紫、根張り不良 | Zn/Feの吸収阻害 | P追肥(骨粉/過リン酸)、pH調整 |
| K | 葉縁枯れ・乾きに弱い | Mg/Ca欠乏を誘発 | 硫酸カリ少量/バランス是正 |
| Ca | 尻腐れ・芯腐れ(新葉) | Mg/K拮抗 | 石灰/カルシウム葉面散布・潅水安定 |
| Mg | 古葉の葉脈間黄化 | Ca/K拮抗 | 苦土石灰/硫酸マグネシウム |
| Fe | 新芽の黄化(葉脈緑) | — | キレート鉄葉面散布・pH見直し |
| B | 芯止まり・花落ち・裂果 | — | 微量要素入り肥料・過石のホウ素入りで補う |
pH矯正:石灰資材の使い分け
| 資材 | 効き方 | 使いどき | 注意 |
|---|---|---|---|
| 苦土石灰 | 穏やか+Mg補給 | 標準。播種2週間前 | 入れ過ぎでpH上がりすぎ |
| 消石灰 | 速効・強力 | 酸性が強いとき | 肥料と同時混合NG(アンモニア揮散) |
| 炭カル | 穏やか | 微調整 | 長期目線で |
塩類集積と肥料焼け
- 症状:鉢縁の白い結晶、葉縁枯れ、生育停滞。
- 原因:濃い施肥・受皿の水滞留・乾湿差の極端。
- 対策:月1回のリセット潅水、施肥は少量多回、受皿の水は捨てる。
連作障害との関係
肥料の偏り・有機物の未分解・病原の蓄積が絡む。輪作と緑肥・堆肥で土を回復させ、偏ったN多用をやめると軽減。
堆肥の使い方(肥料ではなく“地力アップ材”)
- 目安:畝m²あたり1〜2kg(多用しすぎない)。
- タイミング:作付け前に全層10〜15cmへ混和。
- 効果:保水・排水・通気の三拍子+微生物活性。
ボカシ肥の位置づけ
- 油かす+米ぬか+魚粉などを発酵させた“ゆっくり効く有機”。
- 春先は効き遅れやすい→緩効性化成を少量ブレンドで安定。
液肥の黄金比(プランター日常運転)
- 市販液肥を規定の1/2濃度から。開花・結実期は1/1〜3/4へ。
- 2回に1回は清水潅水でECを下げる。
作物別・年間施肥の目安(中間地基準)
| 作物 | 元肥 | 追肥 | 要点 |
|---|---|---|---|
| トマト | N8〜12g/m²相当+苦土石灰+堆肥2kg | 開花・着果ごとに少量 | Ca・潅水リズムで尻腐れ予防 |
| ナス | N10〜12g/m²+堆肥2kg | 2〜3週ごと。高温期はこまめに | 過湿と過乾の振れを減らす |
| キュウリ | N8〜10g/m²+Kやや多め | 登はん後、収穫始期から頻回 | Kで食味・曲がり改善 |
| ダイコン | P・K中心。Nは控えめ | 基本1回だけ(葉色で) | N過多=裂根・辛味 |
| ニンジン | P厚め・N控えめ | 中期に少量 | 発芽確保が命 |
| レタス | N5〜8g/m²+堆肥1kg | 外葉展開期に微量 | 過剰Nで軟弱・病害 |
| タマネギ | 秋の定植前にP・K厚め | 厳寒期は控え、春先にN | 徒長回避で太らせる |
| ジャガイモ | K多め・N控えめ | 蕾期に一度 | 窒素過多=ツルぼけ |
保管・安全・法表示
- 肥料は密閉・乾燥・冷暗所に。吸湿でダマになると溶出にムラ。
- 袋の保証成分表示(N-P2O5-K2O%)を確認。開封日を記録して品質管理。
- 石灰と窒素肥料の同時混合は避ける(アンモニア揮散)。

「量は数字で決める」が合言葉。N目安→ラベル%で逆算すれば、もう勘に頼らなくてOK!
よくある質問(FAQ)
Q1. 有機と化成、どちらが“正解”ですか?
正解は目的次第。土づくりと地力向上=有機、量とタイミングの精密制御=化成。多くの家庭菜園では、堆肥+緩効性化成+必要に応じて有機のハイブリッドが安定します。
Q2. 肥料焼けをしたかも。どうすれば?
鉢ならリセット潅水(鉢容量の2〜3倍の水)、畑は畝間潅水で洗い流し。以後は少量多回へ。
Q3. 尻腐れ果が出ました(トマト/ピーマン)。
Ca不足+乾湿差が原因。潅水リズムの安定、石灰/カルシウム資材の補強、過剰Nを控えます。
Q4. 葉が黄色い…追肥でOK?
新葉が黄化=Fe/微量要素・pH問題。古葉から黄化=N不足が第一候補。“どこから黄化か”で判断し、pHやECも確認。
Q5. プランターで最速に整える方法は?
元肥入り培養土+1〜2週おきの薄め液肥+月1リセット潅水。EC計があると安定します。
Q6. 緩効性を入れたのに効かない…
低温で溶出が遅い可能性。生育初期だけ少量の液肥でブーストして立ち上げ、気温が上がれば緩効が効いてきます。
関連記事で“意図の次段”へ誘導
- 栽培テクニック・基礎知識まとめ(pH/EC/土づくり・ネット張り)
- 野菜別の育て方・収穫カレンダー一覧(作型×施肥の全体設計)
- 保存方法と調理活用のまとめ(収穫後の品質維持)
スニペット対策(冒頭に差し込んでOK)
- 肥料の基本比率:葉=Nやや多め/実=P・K厚め/根=K・P>N。
- 元肥/追肥:元=緩効・根から離す/追=少量多回+潅水。
- 失敗回避:pHを先に整え、ECを上げすぎない。
構造化データ(FAQ)※Headに貼付
※本文末尾に下のショートコードを置いて内部回遊を底上げします。

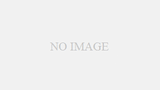
コメント