- 序章|畑の土づくりは「診断→設計→処方」で9割決まる
- 良い畑土の条件(チェックリスト)
- 土質を見極める:3つのクイック診断
- pHとECの初期測定
- 畑の区画設計:畝幅・通路・排水
- 土質別:改善の方向性
- 畑の“硬盤”を疑う(サブソイラーがなくてもできる対策)
- 基準値の目安(一般野菜)
- タイムラインで分かる「畑の土づくり」
- 用量の目安(標準的な畑)
- 新規開墾のケース
- 既存畑のアップグレード
- 二重掘り(ダブルディギング)で根域を広げる
- 緑肥(カバークロップ)で土を育てる
- マルチングの使い分け
- 石灰の選び方と注意点
- 失敗パターンと回避
- 肥料設計の考え方(N-P-Kと作物群)
- 元肥の目安(一般土壌・m²あたり)
- 有機肥料の使い分け(性格を知る)
- 追肥設計(タイミングと量の目安)
- 畝あたりの施肥量をサクッと求める式
- 微量要素と症状の見分け
- 輪作(ローテーション)で土を守る
- 灌水(かんすい)設計:土質別・季節別の型
- 雑草管理:予防7割・除草3割
- 土壌病害と連作障害:代表例と土づくり対策
- 緑肥(カバークロップ)ローテの実用テンプレ
- 土壌害虫(ネキリムシ・コガネムシ幼虫など)への土づくり的対処
- 畑インフラ設計で“土を守る”
- よくあるQ&A(畑×土づくり総仕上げ)
- 運用テンプレ(畝ごとチェックリスト)
- まとめ|畑の土づくりは“設計→処方→継続”で仕上がる
序章|畑の土づくりは「診断→設計→処方」で9割決まる
畑の収量・味・病害リスクは、苗や肥料より土づくりの質で大きく変わります。まず今ある土を正しく「診断」し、畑のレイアウトや排水構造を「設計」してから改良材の「処方」を決める――この順番が近道です。
良い畑土の条件(チェックリスト)
- 団粒構造が発達(手で握るとまとまり、軽く指で崩れる)
- 透水性と保水性の両立(大雨後に水たまりが残らず、乾きすぎない)
- 有機物含量が適正(腐植が1.5〜5%目標)
- pHが作物に合う(多くの野菜でpH6.0〜6.5。例外:ジャガイモはやや酸性寄り可)
- 通気性(スコップが20〜30cmスッと入る/硬盤がない)
土質を見極める:3つのクイック診断
① リボンテスト(手触り)
湿らせた土を指で押し伸ばし、粘土分が多いほど“帯状(リボン状)”に伸びる。砂質→伸びない/ローム→少し伸びる/粘土質→長く伸びる。
② ジャーテスト(沈降)
- 土1、洗剤1滴、水8を透明ビンに入れて振る。
- 数時間〜一晩で砂→シルト→粘土が層状に沈む。層の厚み比で土質を把握。
③ 透水・滞水テスト
30×30cmを深さ30cm掘り、バケツ1杯の水を注ぐ。30分以内に引けば良好。数時間残るなら排水改善(高畝・明渠/暗渠)が必要。
pHとECの初期測定
- pH:試薬紙/メーターで数点サンプリング→平均。pH5.5以下は苦土石灰などで矯正。
- EC:肥料塩類の指標。高い→塩類集積、洗い流し灌水と有機物で緩和。
畑の区画設計:畝幅・通路・排水
| 要素 | 推奨 | ポイント |
|---|---|---|
| 畝幅 | 70〜100cm | 人が片側から届く幅=作業性UP/踏圧回避で土が締まりにくい |
| 畝高 | 10〜20cm(多雨地は25〜30cm) | 高畝で排水◎、乾燥地は低畝で保水◎ |
| 通路幅 | 30〜40cm | 通路は踏む場所=常時固めてOK(雑草抑制に防草シート可) |
| 明渠 | 畝間or区画外周 | 豪雨時に水を逃がす“小さな水路”を設置 |
土質別:改善の方向性
| 土質 | 弱点 | 改善材・方法 |
|---|---|---|
| 砂質 | 保水・肥料保持が弱い | 完熟堆肥・腐葉土・バーミキュライト・ゼオライトで保水とCECを底上げ |
| 粘土質 | 排水・通気が悪い | 粗い川砂・くん炭・パーライト、高畝+明渠、冬の凍結融解で自然砕土 |
| ローム | 維持管理 | 毎年の完熟堆肥2〜3kg/m²で団粒維持、踏圧を避ける |
畑の“硬盤”を疑う(サブソイラーがなくてもできる対策)
- スコップや棒が20cm付近でカチッと止まる→耕盤の可能性。
- フォークで垂直に刺し、前後に揺すって空隙を作る(年2回)。
- 根を深く伸ばす緑肥(エンバク/ライ麦/ソルゴー)で自然破砕。

診断が決まれば半分勝ち!土を“治療”するのはそのあとだよ〜
基準値の目安(一般野菜)
- pH6.0〜6.5(ホウレンソウは6.5前後、ジャガイモは5.2〜6.0でも可)
- 有機物(腐植)2〜5%、容積重0.9〜1.3、CEC 10〜25程度を目標
タイムラインで分かる「畑の土づくり」
- 除草・残渣除去(雑草根・石・根株を撤去)
- pH矯正(苦土石灰など)→1〜2週間休ませる
- 有機物(完熟堆肥/腐葉土)投入
- 元肥設計(化成or有機)
- 耕起(20〜30cm/硬盤があればフォークで破砕)
- 畝立て&明渠
- 定植・播種(土が落ち着いたら)
用量の目安(標準的な畑)
- 苦土石灰:100〜150g/m²(pHに応じて調整)
- 完熟堆肥:2〜3kg/m²(粘土質は多めに、砂質も多めに)
- 元肥(化成14-14-14等):80〜120g/m² or 有機肥料等量
※未熟堆肥や生の牛/鶏ふんはNG(ガス障害・病害リスク)。完熟品を選択。
新規開墾のケース
- 根株・大型石を撤去。雑草は根まで掘り取る。
- 石灰散布→攪拌→1〜2週間の養生(化成肥料と同時は不可)。
- 完熟堆肥・腐葉土を均一散布→耕起。粘土質は川砂・くん炭を1〜2L/m²追加。
- 排水計画:区画外周に浅い明渠、畝は傾斜の下手へ水が流れる向きで。
- 畝立て:70〜100cm幅、10〜20cm高(多雨地25〜30cm)。土が落ち着いたら定植。
既存畑のアップグレード
- 土が硬い:年2回のフォーク破砕+緑肥(ライ麦/エンバク)で根に耕してもらう。
- 過湿:高畝化、畦間に明渠、通路へ砂利or防草シートで泥化防止。
- 乾燥:低畝+有機物増、バーク/わらマルチで蒸散抑制。
二重掘り(ダブルディギング)で根域を広げる
- 畝幅分を深さ30cm掘り、表土を一旦隣へ移す。
- 底土に堆肥・くん炭を軽く混ぜ、突き崩す(混ぜすぎない)。
- 隣の表土を戻し、表層にも堆肥を混和→均す。
機械なしでも通気・保水が改善し、根がスッと下へ伸びる土に。
緑肥(カバークロップ)で土を育てる
| 作物 | 目的 | 播種量の目安 | すき込み時期 |
|---|---|---|---|
| ヘアリーベッチ(マメ科) | 窒素固定・地力UP | 10〜20g/m² | 開花前 |
| ライ麦/エンバク | 根で硬盤破砕・有機物供給 | 10〜15g/m² | 穂立ち前 |
| ソルゴー | 夏の有機物供給・乾燥抑制 | 1〜2g/m² | 草丈50〜80cm |
すき込み後は2〜3週間の分解期間を置いて窒素飢餓を回避。
マルチングの使い分け
- わら/バーク:保水・地温安定・土跳ね防止(病害軽減)。
- 黒マルチ:地温上昇・雑草抑制、雨天作業性UP。
- シルバー:アブラムシ忌避。
石灰の選び方と注意点
| 種類 | 特徴 | 注意 |
|---|---|---|
| 苦土石灰 | Mg補給+安定 | 元肥と同時混和NG |
| 有機石灰(カキ殻) | 緩やか | 効果が出るまで時間 |
| 消石灰 | 即効 | 強アルカリ・取り扱い注意 |

「石灰→休ませる→堆肥→元肥→耕す→畝」この順番を守ると失敗がグッと減るよ!
失敗パターンと回避
- 石灰と窒素肥料の同時投入→ガスで効かない:必ず時差。
- 未熟堆肥を大量投入→窒素飢餓・病害:完熟に限定。
- 畝高が低いのに多雨→根腐れ:高畝+明渠+通路整備。
肥料設計の考え方(N-P-Kと作物群)
肥料は「作物のステージ」と「作物群(果菜・葉菜・根菜・豆科)」で設計します。土づくりの目的は、根を健全に・過不足なく・持続的に養分を供給すること。以下は家庭菜園で扱いやすい基準です。
N(チッ素)
- 葉を育てる原動力。不足→葉が黄化・生育停滞。過多→徒長・病害虫リスク増。
- 葉菜はやや多め、果菜は前半控えめで開花後に効かせるのがコツ。
P(リン酸)
- 根張り・開花結実・糖度と関係。冷え込み時は効きにくくなる。
- 果菜・根菜はPを嫌わない。元肥からしっかり配る。
K(カリ)
- 根・茎の強さ・耐病性・品質に直結。水分調節にも寄与。
- 根菜・果菜で重視。キレの良い味や貯蔵性に効く。
元肥の目安(一般土壌・m²あたり)
- 化成肥料(8-8-8〜14-14-14):80〜120g/m²(土質・作物により調整)
- 完熟堆肥:2〜3kg/m²(砂質・粘土質は多め、ロームは維持量)
- 苦土石灰:100〜150g/m²(pHに応じて・石灰は肥料と同時混和NG)
※具体の施肥量は使用製品のラベル基準を優先。以下は「考え方のテンプレ」です。
作物群別の配分指針(元肥NPKのバランス)
| 作物群 | バランス指針 | ポイント |
|---|---|---|
| 果菜(トマト・ナス・ピーマン等) | N:P:K ≒ 1:1.2:1.5 | 前半N控えめ/開花以降に追肥で持続 |
| 葉菜(レタス・ホウレンソウ等) | N:P:K ≒ 1.3:1:1.2 | Nを切らさないが過多で徒長に注意 |
| 根菜(ダイコン・ニンジン等) | N:P:K ≒ 0.8:1.2:1.5 | 元肥中心・偏り防止。塊根の割れ/二股に注意 |
| 豆類(エダマメ・インゲン等) | N:P:K ≒ 0.5:1:1.2 | 根粒菌でN自給。N過多は着莢不良へ |
有機肥料の使い分け(性格を知る)
| 資材 | 主な栄養 | 特徴 | 使いどころ |
|---|---|---|---|
| 油かす | N | ゆっくり効く。分解に時間 | 葉菜の元肥・果菜の前半 |
| 骨粉 | P | 根・花・実向け。即効〜緩効 | 果菜・根菜の元肥 |
| 魚かす | N・微量要素 | 分解早め。風味あり | 活着後の追肥・寒冷期 |
| 草木灰 | K・Ca | アルカリ性。即効 | 根菜・果菜の味締め/酸性土の補正 |
| 鶏ふん(完熟) | N・P・K | 効き早め。塩分に注意 | 広く。少量分散 |
未熟堆肥・生ふんはNG。ガス障害や病害のリスク増。
追肥設計(タイミングと量の目安)
| 作物群 | 時期 | 目安 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 果菜 | 活着2週間後→着花期→果実肥大期 | 1回20〜40g/m²(化成)を畝肩に、または薄めの液肥 | 株元に近づけすぎない/水と併用 |
| 葉菜 | 外葉展開開始〜収穫まで2〜3週ごと | 薄め液肥 or 少量の化成をこまめに | 徒長に注意。葉色で調整 |
| 根菜 | 間引き後〜肥大開始期 | ごく少量(K寄り) | やりすぎると裂根・二股 |
| 豆類 | つる伸長〜開花直前 | P・K中心に薄め | Nは控えめ(莢つき優先) |
畝あたりの施肥量をサクッと求める式
畝面積(m²)=畝幅(m)×畝長(m)。例:畝幅1.0m×長さ5m=5m²。
化成100g/m²なら、5m²→500g が目安。
微量要素と症状の見分け
- Mg欠乏:古い葉の葉脈間が黄化。→苦土石灰・苦土入り液肥。
- Ca欠乏:先端の生長点不良・尻腐れ(トマト)。→石灰・Ca入り液肥/水分安定。
- B欠乏:芯止まり(アブラナ科)。→ボロン入り資材を微量(過多厳禁)。
輪作(ローテーション)で土を守る
同じ科の連作は土壌病害・害虫を蓄積。3〜4年回しが基本です。
科と代表作物
| 科 | 代表 |
|---|---|
| ナス科 | トマト・ナス・ピーマン・ジャガイモ |
| アブラナ科 | キャベツ・ブロッコリー・ダイコン・コマツナ |
| セリ科 | ニンジン・パセリ・セロリ |
| マメ科 | エダマメ・インゲン・ソラマメ |
| ヒユ科 | ホウレンソウ・フダンソウ |
| ウリ科 | キュウリ・カボチャ・スイカ |
3年輪作例
- 年1:ナス科(果菜)
- 年2:マメ科(窒素固定・地力回復)
- 年3:アブラナ科 or セリ科(根菜/葉菜)
4年輪作例(安定型)
- 年1:果菜(ナス科/ウリ科)
- 年2:葉菜(アブラナ科/ヒユ科)
- 年3:根菜(セリ科/アブラナ科)
- 年4:マメ科+緑肥(ヘアリーベッチ/ライ麦)
小区画では「畝ごとに年札」を立てて管理。接ぎ木苗の活用も有効。
灌水(かんすい)設計:土質別・季節別の型
- 砂質:少量多回数。朝メイン/猛暑日は夕方チェック。
- ローム:表土が乾いたらドッと与えて底から抜く。頻度は週2〜3〜気象次第。
- 粘土質:過湿厳禁。高畝+通気確保。乾きのムラに注意。
共通:指で3〜4cm掘って湿りを確認。天水(雨)後の過湿は中1〜2日空ける。
大雨時のレスキュー
- 畝肩を軽く崩して「逃げ水路」を一時的に作る。
- 雨後は通路の滞水を明渠へ誘導。根の呼吸を回復。
雑草管理:予防7割・除草3割
- スタale seedbed(偽播種):耕す→1週間待って雑草発芽→浅く除草→本播種。
- マルチング:黒マルチ/わら/バークで光遮断&土はね防止。
- 通路は踏んでOK:踏圧で固め、必要なら防草シート+砂利。
- 根から切る:ホー・けずっ太郎等で浅刈り。抜き跡は軽く覆土。

「必要な時に必要なだけ」——肥料も水もそれが合言葉。輪作とマルチで安定感アップだよ!
土壌病害と連作障害:代表例と土づくり対策
ナス科の萎凋・青枯(トマト・ナス等)
- 症状:急にしおれ、葉脈が褐変。導管のトラブルが多い。
- 対策:輪作(3〜4年)・高畝・排水改善・接ぎ木苗・太陽熱消毒・雑草根の徹底除去。
アブラナ科の根こぶ病(キャベツ・ダイコン等)
- 症状:根がこぶ状に膨れる、萎れ。
- 対策:pHをやや高めに維持(苦土石灰)・輪作・乾湿ムラ回避・抵抗性品種。
菌核病・白絹病(広範)
- 症状:地際の白い菌糸・子のう殻、茎の腐敗。
- 対策:通風・株間・マルチで土はね防止、残渣を持ち出す、過湿回避。
土壌消毒(家庭向けの現実解)
- 太陽熱消毒:夏、畝に十分灌水→透明ビニールで密着被覆→2〜4週間。途中でかき混ぜ。
- 石灰窒素:扱い注意。必ずラベル遵守・作付までの待機期間を守る。
緑肥(カバークロップ)ローテの実用テンプレ
緑肥は「土の筋トレ」。有機物供給・病害虫抑制・硬盤破砕・地力回復に効きます。
1年型(春夏作→秋緑肥)
- 春〜夏:果菜(トマト/ナスなど)
- 秋:ライ麦 or エンバクを条播→冬越し→翌春、穂立ち前にすき込み→葉菜へ
2年型(豆を挟んで地力アップ)
- 年1:果菜
- 年2:マメ科(エダマメ)→跡にヘアリーベッチ→開花前に鋤き込み→根菜へ
夏の乾燥地向け
- ソルゴーで被覆→草丈50〜80cmで粉砕・すき込み→有機物を一気に追加。
緑肥すき込み後は微生物の分解に窒素を使うため、2〜3週間の分解期間を置くと安全。
土壌害虫(ネキリムシ・コガネムシ幼虫など)への土づくり的対処
- 耕起のタイミング:幼虫が浅層にいる季節に耕して露出→鳥に食べてもらう。
- 清潔な畝:雑草根・残渣を持ち出し、産卵場所を減らす。
- 物理防除:防虫ネット・苗の首元にカラー(紙カラー)で食害を防止。
- 土を健全に:団粒・排水・pHを整えると、根の再生力が上がり被害に耐える。
畑インフラ設計で“土を守る”
- 資材置場:堆肥・くん炭・砂・バークは雨を避けて保管(流亡と劣化防止)。
- 通路設計:通路は踏み固めてOK。作業動線を短く。
- 水源:雨水タンク+ホースで灌水を楽に。泥はね軽減=病害軽減に直結。
よくあるQ&A(畑×土づくり総仕上げ)
Q1. いつ耕すのがベスト?
土が乾きすぎず湿りすぎない時。塊が拳大で崩れる程度。雨直後や極端な乾燥時は避け、構造を壊さない。
Q2. 粘土質が強すぎてスコップが入らない…
高畝+明渠でまず排水。冬の凍結融解を利用しつつ、粗い砂・くん炭・堆肥を年単位で追加。緑肥の根で自然破砕。
Q3. 砂質で肥料が流れる
堆肥・腐葉土・ゼオライトでCEC(養分保持)を底上げ。緩効性肥料を小分けで。
Q4. 収穫量を上げたいなら、何から?
畝高と排水→団粒(堆肥)→元肥の順。水はけの悪さは全てを台無しにするので最優先で改善。
Q5. 連作避けたいけど場所が足りない
接ぎ木・緑肥・ポット栽培の併用で回避。同一科を隣畝で翌年植えないだけでも効果。
運用テンプレ(畝ごとチェックリスト)
- 収穫後:残渣の持ち出し→簡易耕起→天日干し
- pH測定→必要なら石灰→1〜2週間養生
- 完熟堆肥2〜3kg/m²+元肥→耕起20〜30cm
- 畝立て(幅70〜100cm・高10〜20cm/多雨地25〜30cm)
- マルチ(必要に応じて)→定植・播種
- 追肥・灌水を「少量×タイミング良く」

「排水・団粒・輪作」——この三種の神器で、畑は毎年強くなるよ!
まとめ|畑の土づくりは“設計→処方→継続”で仕上がる
- 診断(土質・pH・透水)→設計(畝・通路・明渠)→処方(堆肥・石灰・元肥)
- 作物群別にNPK配分を変える。追肥はフェーズごとに「少量×的確」。
- 輪作と緑肥で病害をためない。物理的な土づくりを続けるほど収量・品質は安定。

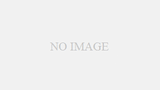
コメント